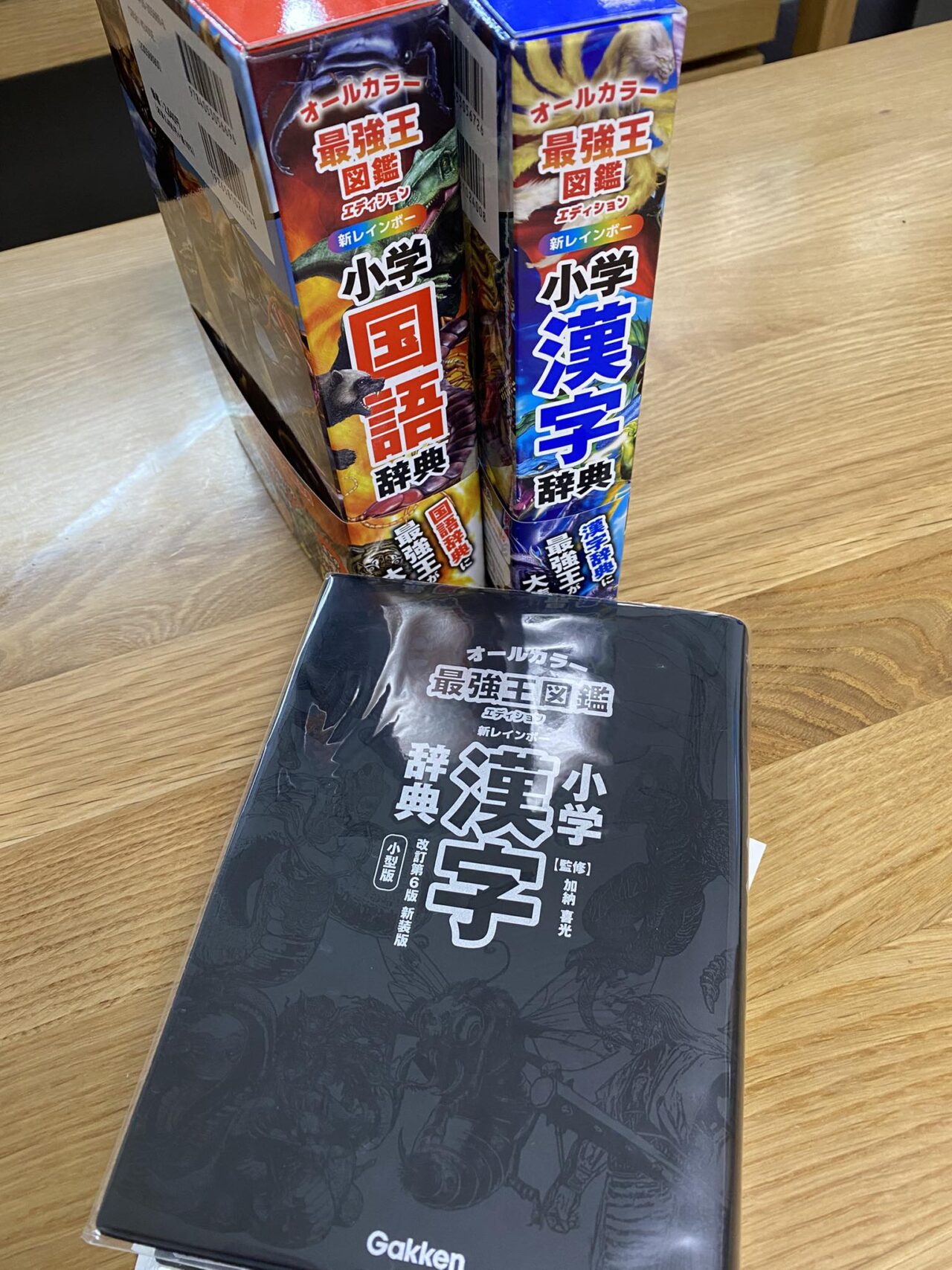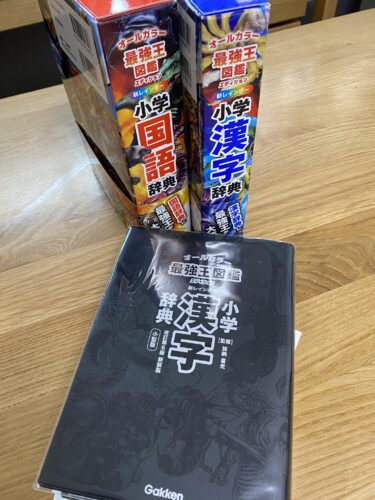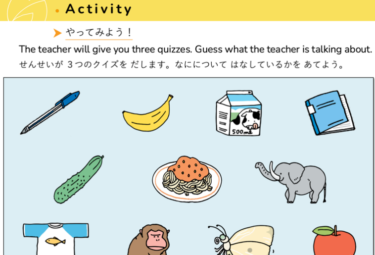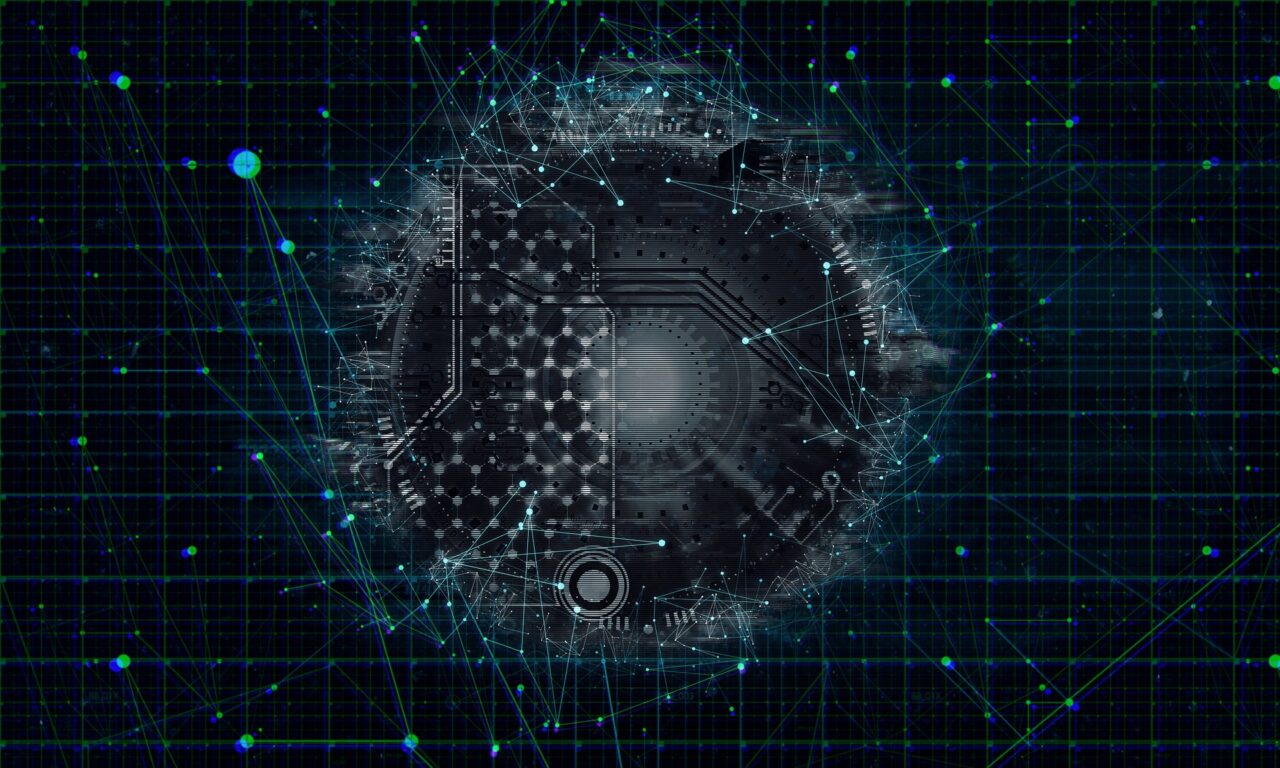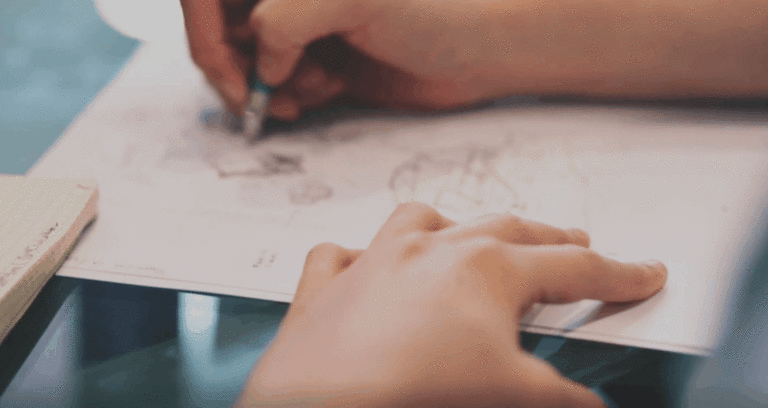学研教室では、「自学自習をできる子に」これを一番の目標として、指導しています。
自学自習、なにからするの?
自分で参考書を読んで、自分で理解して、自分で解いていく、自らすすんで学習して、目標を定めて、それに向かってスケジュールをたて、目標を達成していく…。
なんと、大変なことでしょう。
ただ、塾で講義をきいているだけでは、自ら進んで勉強しているとは言えません。
その瞬間はすぐにその問題がわかるようになり、楽かもしれませんが、それまででその学習を活かした次のステップへ自分ですすむことがむずかしくなってしまいます。
受け身の授業では、Youtubeで動画をみているのとそんなに変わらない状況だと思います。
塾で説明をきく→その例題はわかる→似た問題が解ける→また、塾で説明をきく→その例題はわかる→似た問題が解ける
これをずっと繰り返しています。
これをしてしまうと、楽ではありますが、この先もこのスタイルの学習しかできなくなってしまいます。
将来、大学受験ではどうしょうか?このスタイルを繰り返していると、私大英語だの、共通テスト対策だの、すべての講習を受けることになってしまいます。あっという間に講習でスケジュールは埋まり、それをこなすのに、いっぱいで自ら学習せず、あっぷあっぷ時間に終われて沢山学習したのに…。という気持ちばかりで、自分がどの位置にいるかわからず、不安がいっぱいということになりかねません。
自学自習できていれば、参考書と問題集だけで、解決します。
まずはデジタルデトックスから
辞書をひくなんて、なんてアナログな…。ネットで調べればいいじゃない?それも一つありますよね。
でも、ネット、例えばスマホを横に置いて勉強してしまうと、スマホを見てしまいますよね…。ゲームをしたり、SNSを見たり、友達からLINEがきて返信したり、Youtubeを見たり…。
まずは、スマホを勉強の時に横においておくのは危険です。
まったく、集中できません。
スマホでなんでも調べていた子たちは、スマホがない状態になってしまうと、まったく、手が付けられなくなってしまいます。
まず、小学生のうちから、漢字を調べたり、意味を確認したりすることで、辞書に慣れましょう。
勉強の効率化
すぐに調べられる週間をつけておくと、始まりは国語だけど、数学でも社会でも索引をみて自分の知りたいことにたどり着けるスキルが自然と身につきます。自分で調べることができないというがないように、まずは小学生のうちに辞書に慣れておくことです。
教室では調べるだけですが、家の辞書では、自分だけのものなので、一度ひいた言葉には線をひいておくといいと思います。
2度目同じ言葉を調べたら、「あれ?前にも調べてたな…。覚えておこう。」と思ったりできます。
この2度目に引いた言葉を知るということは、勉強の効率化につながります。
辞書で慣れておくことで、効率化した勉強の方法が身につきます。
時間は限られています。講習を受けて楽を時間を短縮することもできますが、自学で効率よく学習するには、次のようなやり方になります。
問題集を1周やってみる。→間違えてところをチェック→2周目は間違えたところ解く→さらに間違えたところを解く→3周目はさらに間違えたところを解く
3周、べったり問題集をやるのではなく、このようにできなかったところだけをやればいいのです。それで3周です。1周目ですべてできてしまったら、その問題集では学習するところはありません。次の問題集に進みましょう。
このように、間違えたところをやっていくことで、苦手なところが明確化されますし、その時に教室で相談したらいいと思います。間違えた回答をみれば、先生は「あーこういう勘違いしたのね」「なるほど、これがわからないのかな」などと考えて指導してくれます。教えてくれる時もあるし、どこからつまづいているのか、教えてくれます。それが学研の先生の役目です。
学研では教材が無料なので、どんどん苦手な箇所の教材を渡すことができます。きれいなプリントで新しく取り組むことができますし、問題集ごと戻るのではなく、プリント1枚からやり直すことができるので、そこが学研のいいところかなと思っています。
常に、指導者同士で、この問題が解けないときはこの地点に戻ることを教えあっていますし、いろんな教室での経験を吸収して、先生自身も学習していっています。
意識改革
意識改革だなんて、大げさですね。
ただ、このちょっとしたことで、自学自習をするという意識につながります。
知りたいことを辞書で調べると、その意味が載っていて、知ることが出来る。
とても単純なことですが、大事な成功体験の一つとなります。
それと、保護者にとってもいいことがひとつ。お子さまの「これなに?」みたいな調べればわかるような質問に、付き合って一緒にスマホで調べたりしていませんか?
そんなのは、「調べて分かったら、ママにも教えて~」と言っておけばいいと思います。子どもは調べるミッションが与えられて、ママに伝えるという責任がでてきます。辞書引き学習ができていれば、素直に調べて、「ママ、これはね~」と勇んで教えてくれます(笑)。知ってても、教えてくれてありがとうって感じで聞けば、いつでも調べて教えてくれます。
調べて教えてなくていいし、学習にもなって、子どもの自己肯定感もあがって、もうwin-winです。